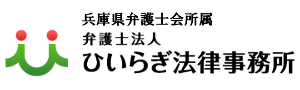自筆証書遺言とは?全部自筆でなければならないのか?

最終更新日 2024年6月30日
「自筆証書遺言とは?」
「全部自筆でなければならないのか?」
今回は、そうした疑問にお答えします。
自筆証書遺言とは
遺言は、民法の中で作成方法が規定されています。
普通方式の遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、普通方式の中で最も簡単に作成できるのが「自筆証書遺言」です。
民法第968条に自筆証書遺言の作成上限のルールが規定されており、これに従っていないものは無効になる可能性がありますから作成にあたっては注意を要します。
原則自書
まず、遺言の内容をかならず自筆で記載して、作成した日付・遺言者の氏名を自書して印鑑を押すことがルールとして規定されています。
自筆でなければならないということはパソコンなどで作成したものは無効になります。
日付は、年月日をすべて記載します。
遺言は生前に何度でも書き直すことができます。
そして、前に書いた遺言と後の遺言の内容が矛盾する場合は前の遺言は撤回したことになります。
遺言は、被相続人の最後の意思を尊重するものですから死に近い日付の遺言を有効な遺言として扱います。
このことから、作成日付は非常に重要となります。
かつて「昭和41年7月吉日」と記載した遺言を無効とした裁判例がありました。
氏名については、芸名やニックネーム、通称名であってもそれが誰のことを示しているかが容易に認識される名前であれば有効な遺言となる可能性が高いですが、特に問題がないのであれば本名を記載するのがよいでしょう。
印鑑は、実印である必要はなく認印で押印して構いません。
財産目録は自書でなくてよい
財産目録について規定されています。
1項の本文の中に自筆で財産の内容を記載しても構いませんし「私は別紙財産目録記載のとおりの財産すべてを妻裕子に相続させる」や「私は別紙財産目録①記載の財産を妻裕子に、別紙財産目録②記載の財産を長男正弘に相続させる」などのように本文とは別に財産目録を作成しても構いません。
この場合の別紙の財産目録については、自筆のものでなくてもよく、パソコンで作成されたものでも有効です。
ただし、その場合には財産目録の各ページに氏名を自書し、印鑑を押します。
氏名は自書でなければいけません。
この規定は平成31年1月13日に施行された法律改正により変わりました。
以前は自筆証書遺言ではパソコンなどの作成は認められていませんでした。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
 自筆証書遺言の方式を利用することのメリットは、費用がほとんどかからずいつでも作成や書き直しができる点にあります。
自筆証書遺言の方式を利用することのメリットは、費用がほとんどかからずいつでも作成や書き直しができる点にあります。
一方デメリットとしては、書き方のルールを含め法的な不備があれば遺言自体が無効になってしまうことです。
さらに、紛失のおそれもあります。
また、公正証書遺言と異なり誰も作成に関与しないため、遺言作成時の意思能力を証明する人がいませんから、後で他の相続人などから無効を主張される可能性があります。
また、自筆証書遺言に基づいて各機関で手続きをするためには家庭裁判所で「検認手続き」を受けなければなりません。
検認手続きは、相続人立ち会いのもとで遺言の現状を確認するものです。
法務局による自筆証書遺言保管制度
 令和2年7月10日より遺言に関する新たな制度がスタートしました。
令和2年7月10日より遺言に関する新たな制度がスタートしました。
自筆証書遺言を法務局でチェックし、保管してもらえる制度です。
法務局によるチェックは、上述した民法第968条の作成上のルールに不備がないかをチェックしてもらえますから、この制度を利用することで、後日記載方法の不備により無効となることはなくなりました。
また、遺言者の死亡後50年間は法務局に原本が保管されますから紛失のおそれもありません。
さらに、この制度を利用した自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要です。
検認手続きは、遺言の効力発生時の遺言の状態を確認し、万一後日偽造や変造があった場合でも容易に判明できることを目的とするものですから、法務局で保管されている以上偽造や変造のおそれがないためです。
法務局による自筆証書遺言保管制度は、利用料も3900円とリーズナブルです。
ただし、上記の民法968条以外の内容チェックや遺言者の意思能力の確認までを法務局がしてくれるわけではありません。
不備があると遺言自体が無効になる可能性があるので、あまりお勧めしません。
まとめ
今回は、自筆証書遺言について解説しました。
法務局による自筆証書遺言保管制度ができたことにより、かなり本来のデメリットがカバーできるようになりましたが、やはり公正証書遺言ほど完全な遺言とはいえない部分もあります。
遺言の作成を検討されている場合は、作成方法も含めて一度弁護士にご相談ください。
最終更新日 2024年6月30日